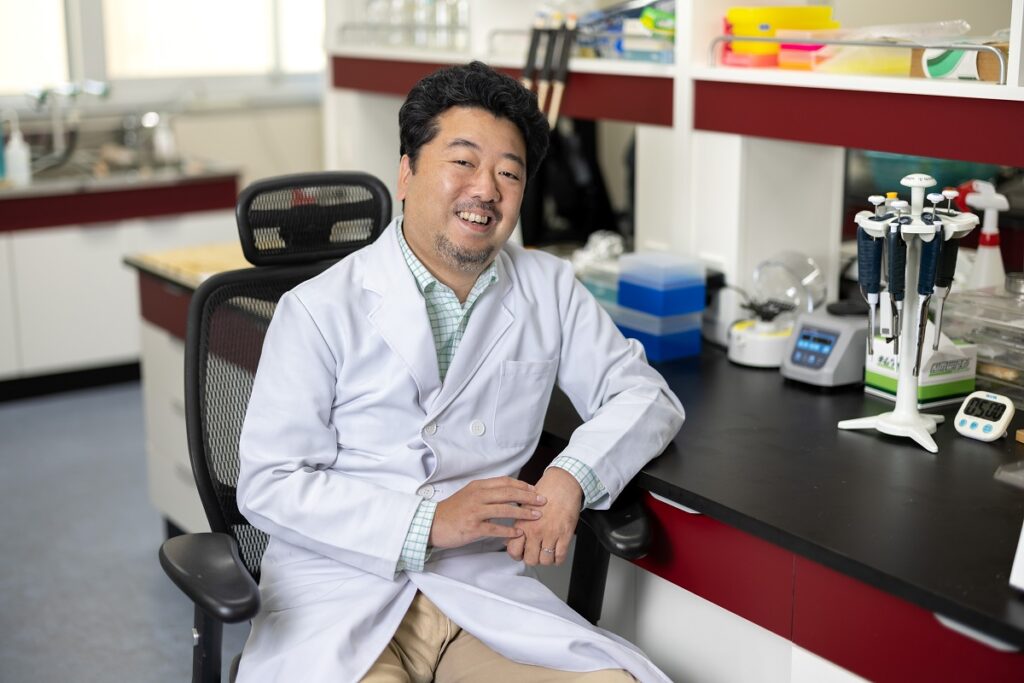
【卒業年】
2005年
【現在の所属】
大阪大学大学院歯学研究科
歯科生体材料学講座
講師
佐々木先生が歯学分野の研究に進まれる動機はどのようなものだったのでしょうか?
歯学部卒業後は、歯の被せものや入れ歯の治療を専門とする講座に在籍しつつ、歯科材料の研究や開発を行っている歯科生体材料学講座(旧歯科理工学教室)で大学院生としての研究をスタートさせました。診療技術や研究方法など学ぶことが多く大変な期間でしたが、大学院4年生のころに再生医療の役に立つであろう世界で初めての技術を確立することができました。歯学部を卒業したときには研究者になろうとは考えてもいませんでしたが、自分が生み出した技術を発展させるべく大学院修了後も研究をコツコツ続けていた結果、海外留学する機会にも恵まれ、研究者として頑張っていこうと決意を固めました。
海外留学について、教えてください。
2015年8月から2年間、アメリカのミシガン大学歯学部に研究留学をしていました。ミシガン大学では大阪大学歯学部で実施していた研究とは少し異なる分野を担当したことから、専門用語を交えながら英語で研究を進めることに多少の難しさはありましたが、それ以上に新しい環境で、新しい研究の背景や技術を学べたことは研究者として本当に貴重な経験となりました。また、私は妻と当時生後7か月の子供を連れて渡米しました。もちろん、大変なこともありましたが、今でも当時の思い出話しをすることもあり、海外生活を通じて家族の絆が深まった気がしています。今も昔も海外留学は、自ら「留学したい!」と周りに発信しなければ機会は巡ってきません。大阪大学歯学部には留学を経験した教員が数多く在籍していますので、海外留学に興味があったり、留学をしたいと思ったら遠慮せずに我々に声をかけてください。
今研究されている内容について、わかりやすく教えてください。
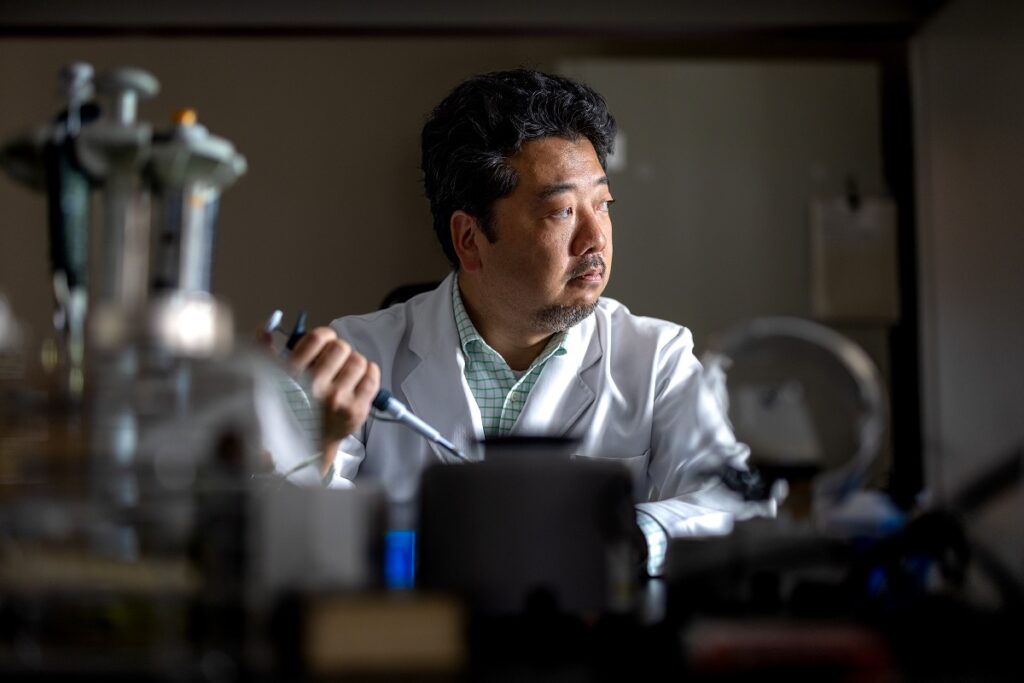
試験管のなかで歯の神経(歯髄)や骨といった臓器・組織を人工的に作製する技術開発や、人工的に作製した組織に血管を誘導するための基礎研究を行っています。歯髄や骨から採取した細胞を増やして集め、さらに特殊な環境で育てることで、歯髄や骨と似た特徴をもった生体材料を作製できることが分かっています。歯周病で骨が少なくなってしまった歯ぐきや、むし歯で歯髄を除去してしまった歯に対して、こういった人工組織を移植することで、失った組織を再生させることができるのではないかと考えています。また、試験管のなかで作製した人工組織を使って、新しい薬剤を探索できるとも考えられており、こういったヒトの臓器・組織を模倣した生きた人工材料を作る研究は注目を浴びています。
今後の未来ではどのような新しい歯学分野の研究が期待されると思いますか?
これまで歯学分野では金属、セラミックやプラスチックを用いた治療がほとんどでしたが、これからは細胞や生理活性タンパク質を治療に利用するための研究が進むと考えています。再生医療の有用性が世界で注目されてからもうすでに20年以上が経過しましたが、細胞やタンパク質といった“なまもの”を利用した歯科治療は極めて少ないのが現状です。歯周病を治療するための世界初のバイオ医薬品はここ大阪大学歯学部で開発されましたが、骨や血管、歯の神経(歯髄)などを再生するための生理活性タンパク質・アミノ酸製剤を開発する研究は今も続いています。さらには、幹細胞を使って歯周病や歯髄の炎症、さらには口の中にできたガンを治すための研究も進んでいます。こういった歯科医療技術を患者に届けるための研究が大阪大学歯学部では多く実施され、今後の発展が期待されています。
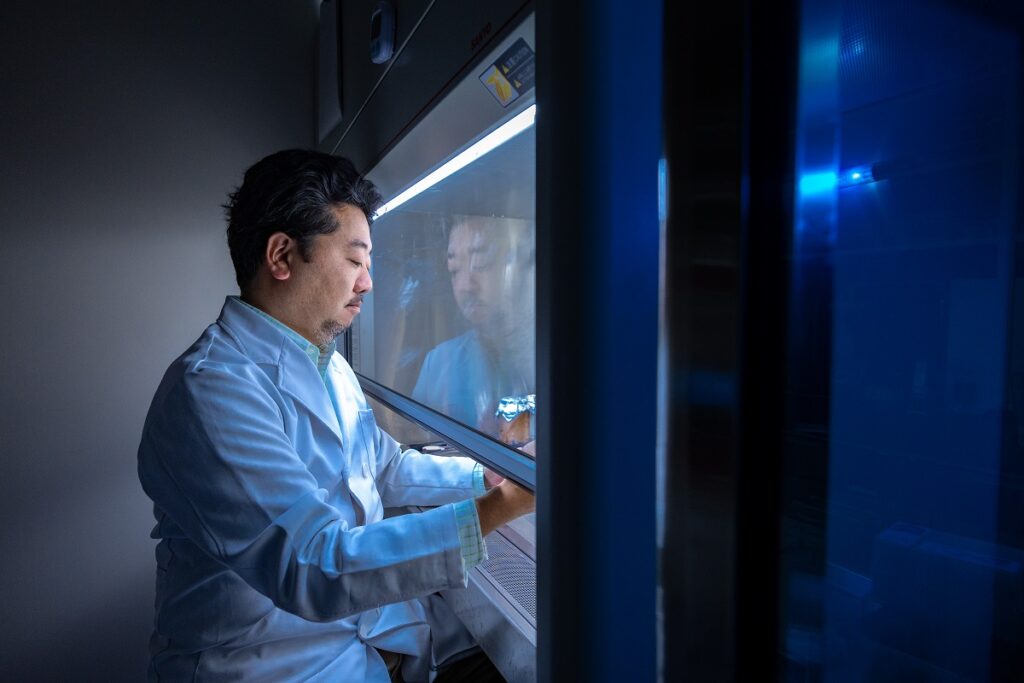
歯学部を目指す高校生・受験生のみなさんへエールをお願いします。
歯学部を卒業する際にはほぼ全ての学生が一様に歯科医師免許の取得を目指します。一方で、歯科医師となった後の進路は多岐にわたります。一口に歯科医師といっても、口腔外科、矯正歯科、小児歯科など様々な分野があり、さらにはそれぞれの分野で多くの研究がなされています。大阪大学歯学部では、一流の臨床医となるためのプログラムはもちろんのこと、世界に通用する最先端の研究を学び実践できる環境があります。是非、大阪大学歯学部で私たちと一緒に最先端の歯科医学を開拓しましょう!
