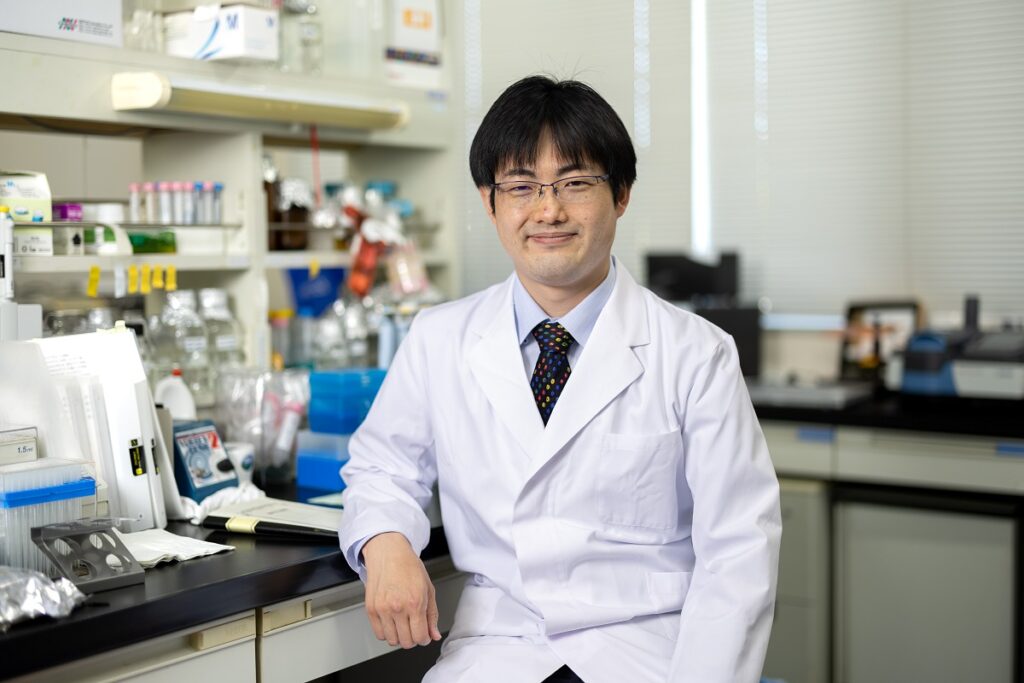
【卒業年】
2005年
【インタビュー当時】
大阪大学大学院歯学研究科
バイオインフォマティクス研究ユニット
准教授
【現在】
医薬基盤・健康・栄養研究所 細菌情報学プロジェクト
プロジェクトリーダー
山口先生が歯学分野の研究に進まれる動機はどのようなものだったのでしょうか?
私が歯学部に入学したのは1999年でした。実家が歯科医院を開業していたこともあり、入学したときは漠然と将来は歯科医師になるとしか考えていませんでした。しかし、3年生の細菌学の講義の一環で、う蝕(虫歯)に対するワクチンを作るという英語論文を読んで研究に興味がわきました。当時の口腔細菌学教室(現 微生物学講座)におられた寺尾 豊 先生(現 新潟大学教授)と川端 重忠 先生(現 大阪大学教授)が丁寧に実験手法について指導してくださり、学部生のときから実際に実験させてもらうことができました。研究に携わって強く印象に残っているのは、研究というのはまだ誰もわかっていないことを調べるので、年齢や経験に関係なく、最新の知識というのは常に学び続けている人が獲得するのだということです。
大学卒業後の進路ですが、当時は研修医が義務でなかったので6年生のときに決める必要がありました。悩みましたが、自分には臨床よりも研究のほうが面白そうだったので、歯科医師としての業務がある臨床系講座ではなく、完全な研究者となる基礎系講座の大学院生として入局することにしました。
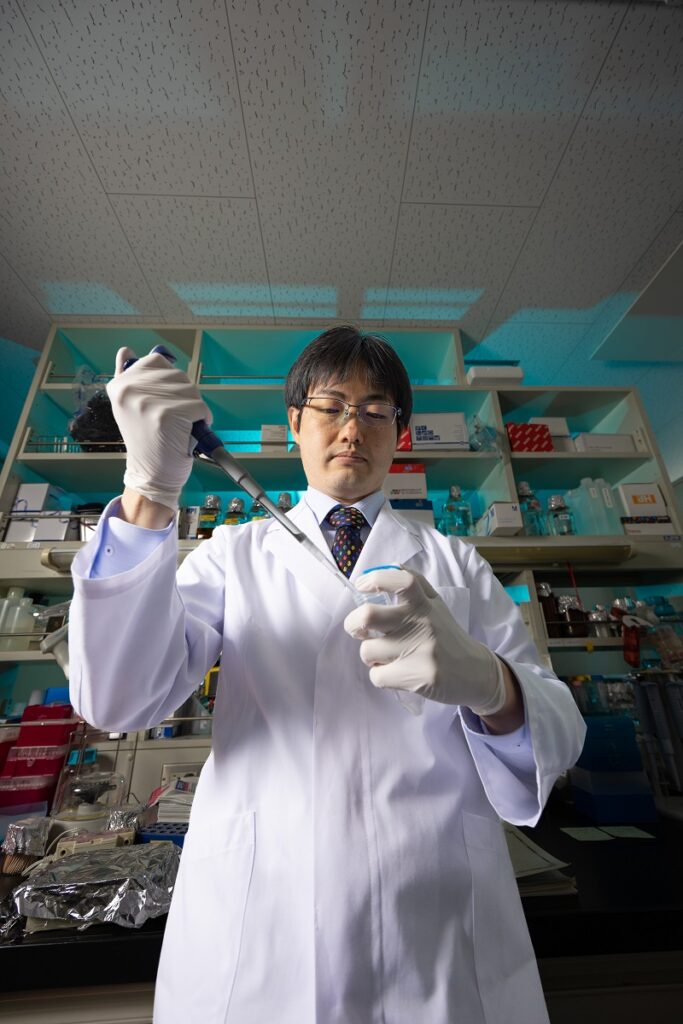
今研究されている内容について教えてください。
現在私は肺炎球菌という細菌について研究しています。肺炎球菌は、分類上は口の中にいる無害な細菌に非常に近い細菌です。実際に、肺炎球菌自身も健康な子供の口からしばしば分離されることが知られています。その一方で、名前のとおりに肺炎の主な原因細菌であり、肺からさらに血液中に菌が侵入して増殖する敗血症という病気や、脳や脊髄を覆っている髄膜というところに炎症を起こす細菌性髄膜炎という命に関わる病気も引き起こします。
このように同じ病原体が様々な症状を起こす原因の探索をしています。具体的には、軽い症状の人と重い症状の人から分離された肺炎球菌を集め、ゲノム配列を解読してどこが違うのかをスーパーコンピューターを用いて探します。違う部分が本当に病気に関わっているかについて、細菌の遺伝子操作をして病気を起こす力が変わるかということを実験で確認します。
また、感染症は細菌とヒトの相互の応答によって引き起こされるので、ヒト側の要因で病気を重症化させるものがないかについても研究しています。このように病気のメカニズムを明らかにすることで、新しい治療法や予防法を作ろうとしています。
今後の未来ではどのような新しい歯学分野の研究が期待されると思いますか?
現在、シーケンサーという遺伝子配列を解読する機械の能力と、ディープラーニングなどの機械学習に基づいた情報解析技術がすごい速度で発展しています。そのために、歯学分野だけでなく医歯薬生命科学分野において、今までは調べようがなかったようなことがどんどん明らかになってきています。例えば、歯科に関連する分野では、口の中に住み着いている細菌たちが全身の病気を引き起こしたり、逆に健康を保つメカニズムが分かってきました。今後は、口に住んでいる菌のバランスなどを整えることで、全身の健康状態を改善したり、病気への治療効果を高めるような方法の研究が進んでいくのではないかと思っています。そのためには、医学部や薬学部、さらには工学部や理学部などと手を組んで行う、異分野連携型の研究推進体制が必須になってくるでしょう。
一方で、現在の自分は、自身が大学に入学した頃には想像もつかなかった研究をしています。それを踏まえると、実際の未来では、いま想像もつかないような新しい技術や分野の研究がされていると期待しています。

歯学部を目指す高校生・受験生のみなさんへエールをお願いします。
大阪大学歯学部の良い点として、国内トップレベルの総合大学の一部であることが挙げられると思います。色んな分野の世界トップレベルの研究者がたくさんいますし、研究の設備も整っているので、本気になればかなり面白いことができます。学部学生のときから研究に関わることも可能で、歯学部でも何人もの学部学生さんが授業の終わった後などに研究を行っています。
歯科医師としての臨床業務や研究が実戦とするならば、高校で学ぶ内容は筋トレなどの基礎に該当します。実戦で筋トレの動作がそのまま使えることはないですが、高いパフォーマンスを発揮するのに基礎は欠かせません。受験勉強は大変だと思いますが、今頑張ったことは後の人生でも必ず役に立ちます。
堅い話を続けてしまいましたが、大学入学後の生活は楽しいこともたくさんあります。特に歯学部は6年間一クラスで過ごすので、一生の付き合いになる友人ができると思います。大阪大学歯学部で皆さんに会えるのを楽しみにしています。
