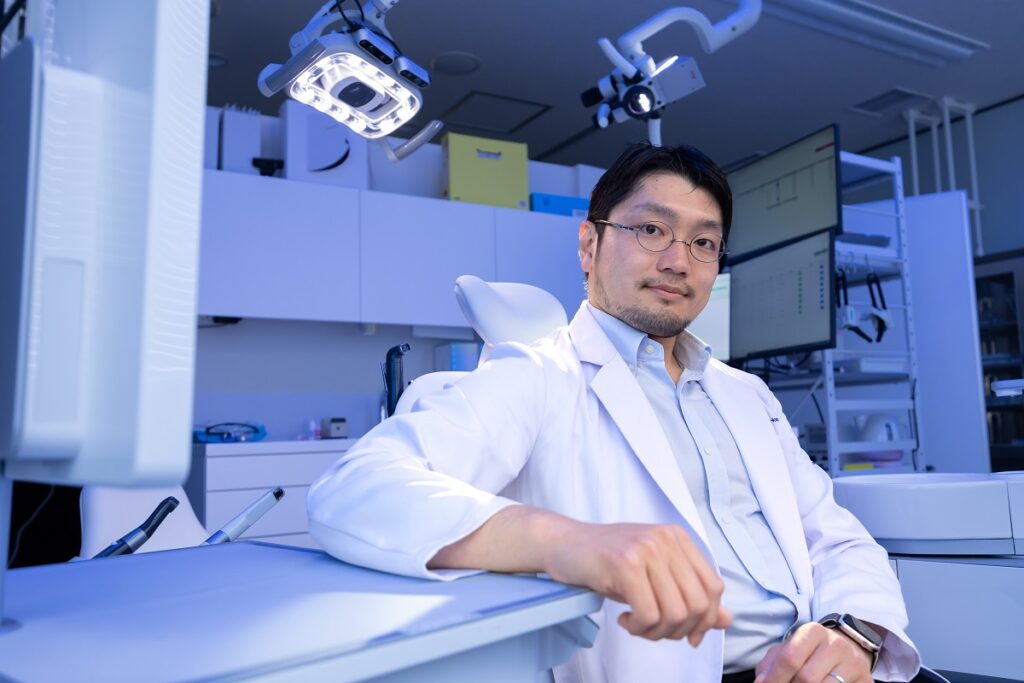
【卒業年】
2016年
【現在の所属】
大阪大学歯学部附属病院
オーラルデータサイエンス共同研究部門
特任助教(常勤)
岡先生が歯学分野の研究に進まれる動機はどのようなものだったのでしょうか?
私が歯学部に入学したのは、歯科医師になって実家の歯科医院を継ごうという安直な考えからでした。歯学部に入ってみると、みんな様々な理由で歯学部に入学したことを知りました。入学後は一般教養、基礎科目、臨床科目、病院実習と様々なことを学習・経験し、またどのような研究がされているかも学ぶことができました。さらに海外派遣プログラムでは、ワシントン大学を訪問し、海外での歯科医療教育や臨床に触れることもできました。
歯学部を卒業して歯科医師免許を取得すると、研修歯科医として1年間臨床研修を受けます。多くの方はこの期間に研究の道に進むかを検討しますが、歯学部卒業までに臨床・研究どちらの道に進むかをすでに決めている方もいます。私は最後まで悩みましたが、最終的には大学院への進学を決めました。
私が大学院に進学した理由は、もう少し歯科を理解したいと思ったからです。臨床の道に進んでも研究の道に進んでも、最新の歯科医学についていくためには勉強し続けなければいけない点は同じです。しかし、臨床だけでなくその根本原理への理解を深めるために研究を経験してみたいと考え、大学院へ進学しました。大学院では医療情報の研究を行い、その一環としてNEC中央研究所の研究インターンに参加し、ベクトル型コンピュータの計算高速化などに取り組みました。

今研究されている内容について教えてください。
今私は、歯科診療を理解できるAIを作る研究をしています。世間ではAIがどのように利用されているでしょうか?例えばAIを用いた自動車の自動運転技術は、ドライバーの疲労を軽減させ、また衝突事故などの起こる確率を下げることにより、ドライバーや歩行者の安全性を向上させています。このような技術開発は数十年前から取り組まれており、現在ようやく市販車に広く導入されるようになりました。私は歯科医療においても似た仕組みが必要であると考えています。つまり診療を何らかの方法でモニタリングし、AIが適切に介入することにより、術者の負担を軽減させ、患者への安全性を向上させる仕組みです。この仕組みの実現を目指した基盤づくりと、歯科診療とはどのようなものなのかという構造の解析に、現在私は取り組んでいます。
今後の未来ではどのような新しい歯学分野の研究が期待されると思いますか?
歯科医学は人々の口の健康を守る科学ですので、人や細菌や材料に対する研究は広く行われており、当然これからも発展していくと思います。しかし近年、様々なデバイスから情報を取り出すことができるようになってきたことから、診療中の様々な機器からも情報が取得できるようになってきました。このようにして得られる診療中のデータを歯科と情報の知識を用いて解析することで、今まではできなかった新たな発見が得られる可能性があると私は考えています。

歯学部を目指す高校生・受験生のみなさんへエールをお願いします。
歯科医師になりたい方や、口に関わることに興味のある方は、間違いなく歯学部に入るべきです。また、歯学部に入るのは歯科医師になりたい人だけでは、と思っている方にお伝えしたいのですが、歯学部に入っても歯科医師以外の仕事はできます。歯学部に入ることによって、口に関わる未知の世界を見ることができるようになるので、他にやりたいことが見つかればその道に進むこともできます。大学に入るということは自分の進路を狭めるのではなく、むしろ自身の可能性を広げるということなのです。
