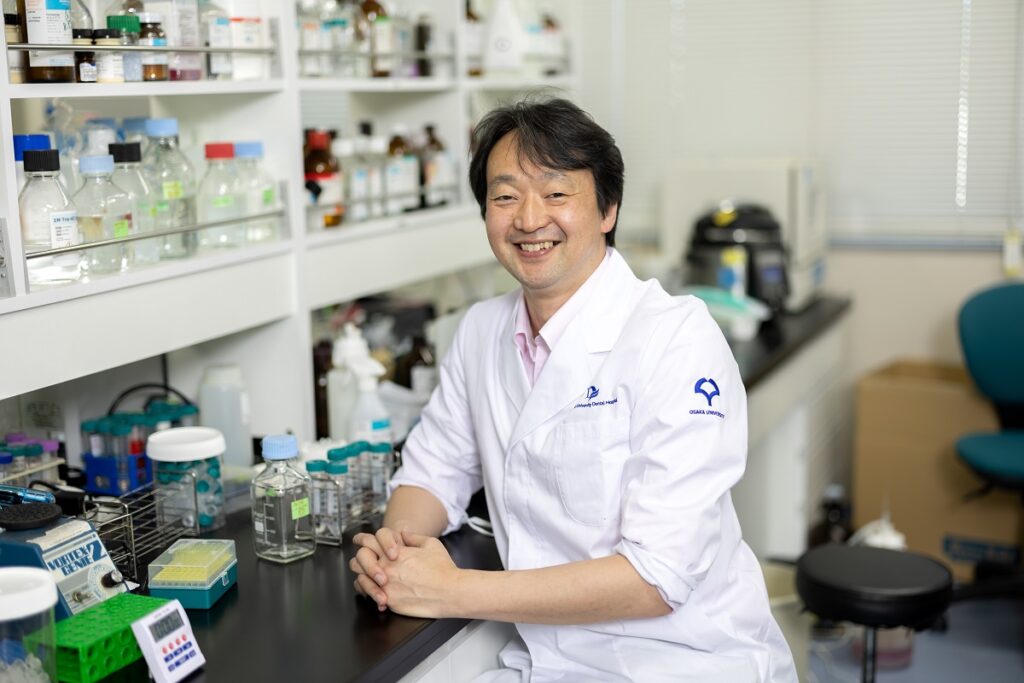
【卒業年】
1998年
【現在の所属】
大阪大学大学院歯学研究科
生化学講座
准教授
波多先生が歯学分野の研究に進まれる動機はどのようなものだったのでしょうか?
父が歯科医であったことから、幼少のころから歯医者という職業を身近に感じていました。患者さんに説明するための歯の模型や使用しなくなった治療器具などを見て触って育ちましたが、幼いころは特に興味はありませんでした。しかし、大学で歯学を学び実際に患者さんを治療するようになると、歯だけだなく私たちの体全体が非常に緻密なプログラムに基づいて機能していること、また最善の治療を行うために治療器具が巧妙にできていることを学び、その仕組みに興味を持ちました。それと同時に、未だ解決されていない謎や問題点が多く残されていることも知り、さらに深く研究したいと思い歯学分野の研究に進みました。

今研究されている内容について教えてください。
口の中には歯だけでなく、骨、軟骨、歯肉、神経など様々な組織があります。また、歯も単一の細胞ではなくエナメル質や象牙質といった形も働きも異なる様々な細胞から構成されています。一つの受精卵から発生し同じDNAを持つはずのこれら細胞が、なぜ全く異なる形や機能を持っているのか、その分子メカニズムを歯や骨に大事な遺伝子の働きに注目して研究しています。歯や骨の遺伝子が特定の細胞だけで働くメカニズムを明らかにすることで、歯周病により無くなってしまった骨や歯を再生する画期的な治療法の開発に貢献したいと考えています。
今後の未来ではどのような新しい歯学分野の研究が期待されると思いますか?
これまでの歯科治療や歯科医学の研究は、歯の詰め物や入れ歯の材料をどのように改良するかといった研究が主体でした。しかし、最近の技術革新により遺伝情報を有するヒトゲノムの解読が完了し、これまで未解決であった病気の分子メカニズムが解明されつつあります。なかには、これまでの予想を覆す画期的な発見もあり、治療への応用が期待されています。将来的には、これら新しい生物学的知見を基盤として、患者さんの遺伝情報にあわせたオーダーメード治療や失った歯の再生などが可能になることに期待しています。

歯学部を目指す高校生・受験生のみなさんへエールをお願いします。
大阪大学歯学部は歯科医師になるための国家試験だけを目標にしている学部ではありません。歯科医学の講義だけでなく、最先端の研究を実際にやってみたり海外の歯科大学と交流をしたりと、6年間を有意義に過ごせると思います。
